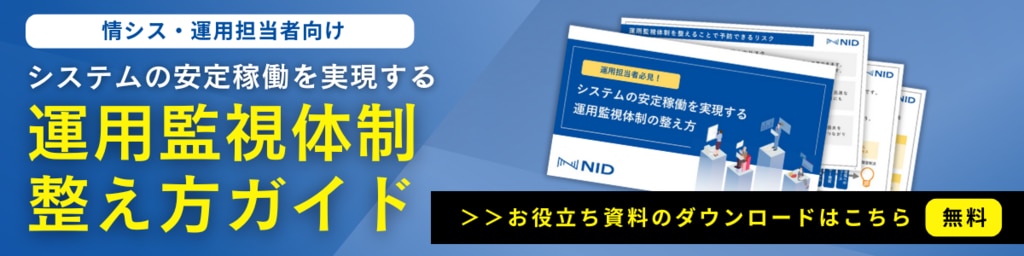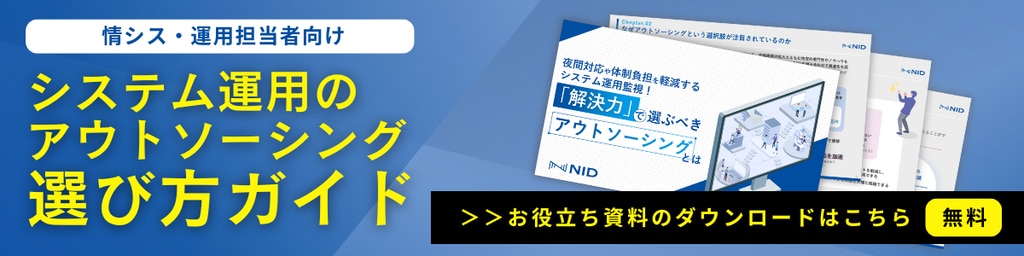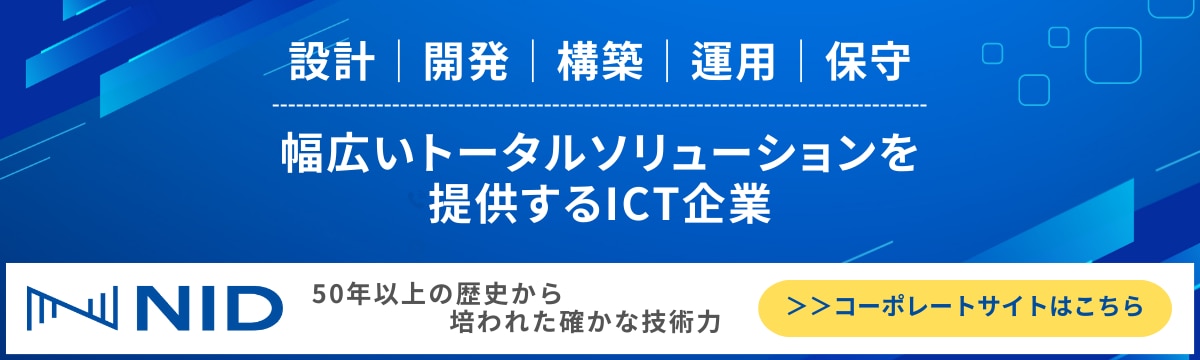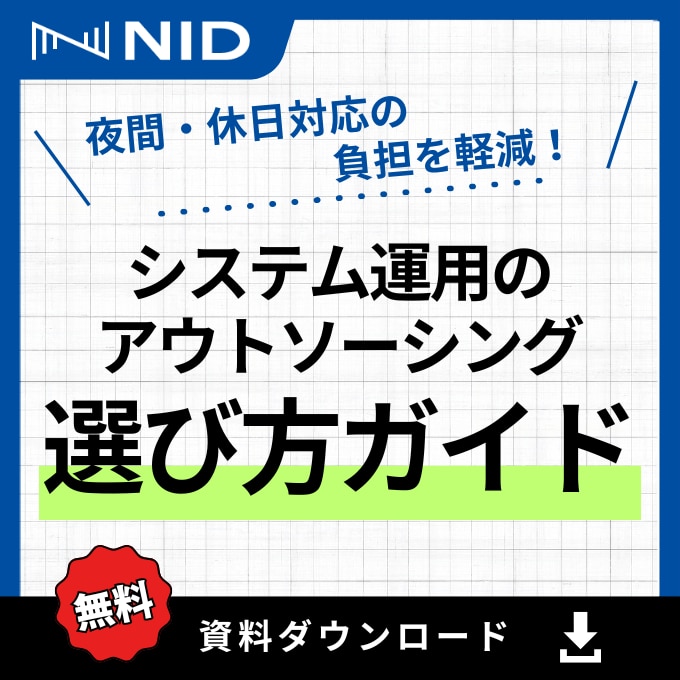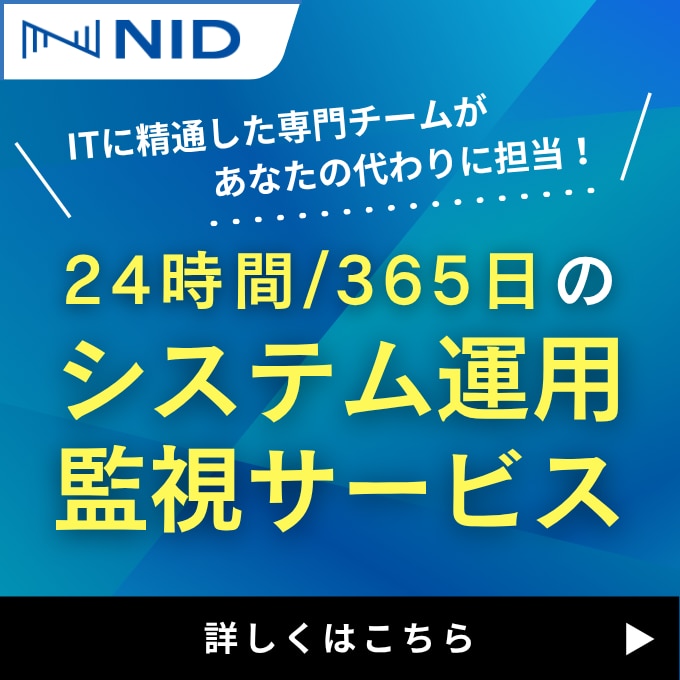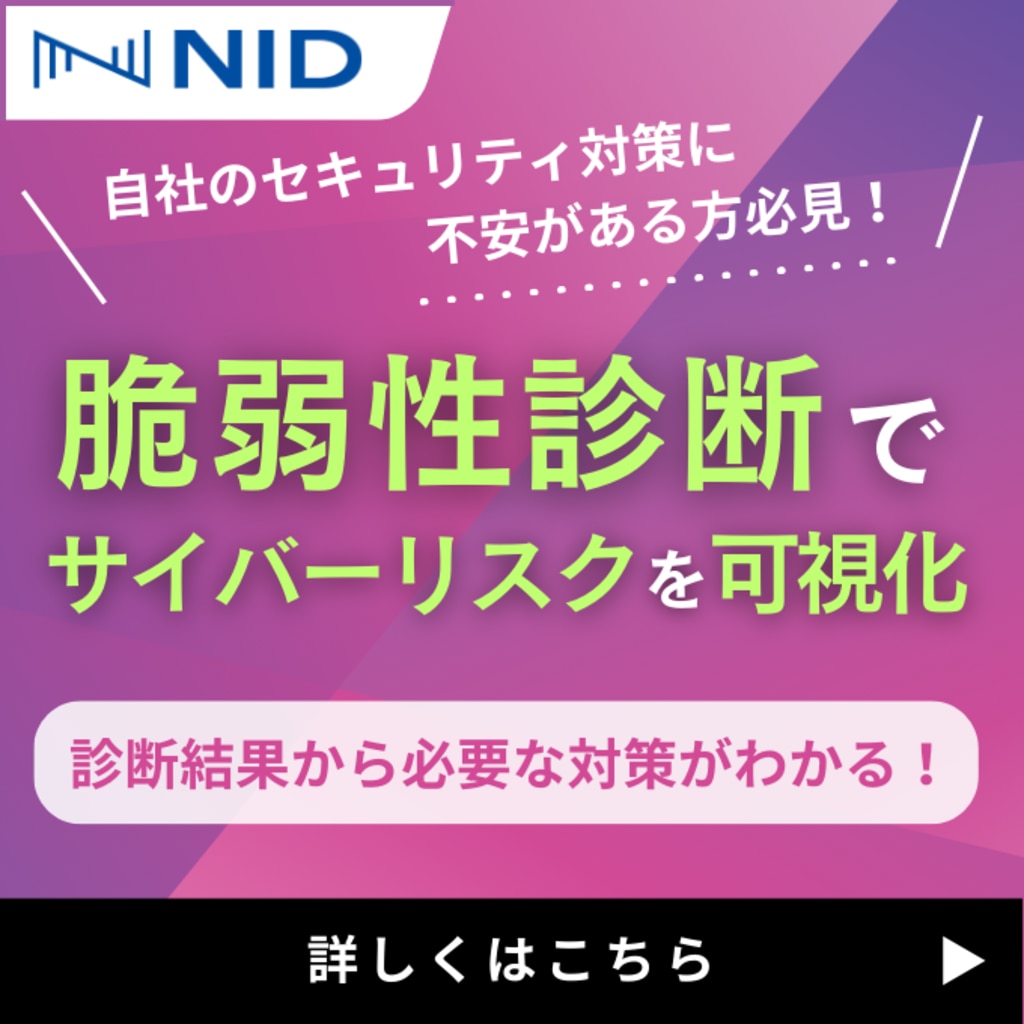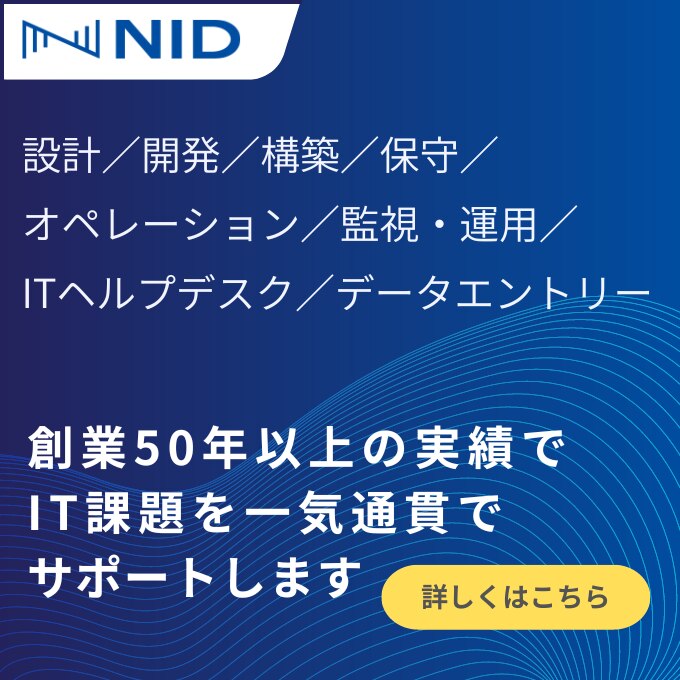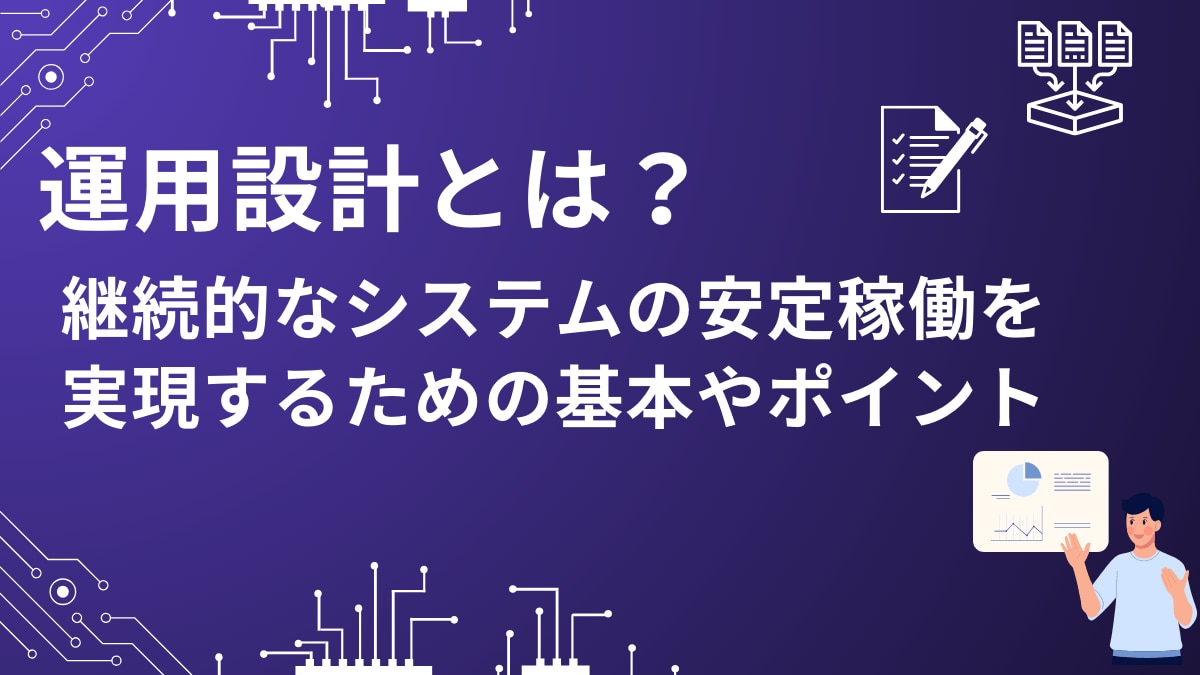
運用設計とは?継続的なシステムの安定稼働を実現するための基本やポイント
本記事では、システム運用の土台となる運用設計に着目し、その重要性や具体的な検討項目、進め方のポイントを解説します。
システムの安定稼働と効率的な運用保守を実現するためには欠かせないプロセスなので、ぜひ参考にしてください。
INDEX[非表示]
- 1.運用設計とは?
- 1.1.開発設計との違い
- 2.運用設計の種類
- 3.運用設計のメリット
- 3.1.運用開始の円滑化
- 3.2.運用範囲の明確化
- 3.3.障害・トラブルの最小化と適切な対応
- 4.運用設計で検討すべきおもな項目
- 5.運用設計のポイント
- 5.1.可用性を優先する
- 5.2.機密性を重視する
- 5.3.完全性を担保する
- 5.4.運用設計の外部委託を検討する
- 6.運用設計からシステム運用監視まで、トータルサポートならエヌアイデイにご相談ください
- 7.まとめ
運用設計とは?

運用設計とは、システムが稼働したあとの運用方針や手順、管理方法を具体的に定義するためのプロセスです。システムが実際に稼働している状況を想定しながら、運用保守・監視、障害やトラブル対応などに関するシステム設計や業務設計をおこないます。あらかじめ運用の仕組みを設計しておくことで、システム運用時の混乱を防ぎ、システムの安定稼働を確保することができるでしょう。
実際のシステム運用では、複数の人や組織が関わり、場合によっては外部の事業者と連携して作業を進めるケースもあります。そこで、事前に運用設計をしっかりおこなっておくことで、関係者ごとの作業範囲や役割分担、コミュニケーションルールが明確になり、スムーズな連携が可能になります。
また、トラブル発生時の対応手順や責任範囲をあらかじめ定めておくことで、非常時の混乱やリスクを最小限に抑えられるでしょう。
開発設計との違い
開発設計は、システムをどのように作りあげるかにフォーカスし、ソフトウェアの仕様やデータベースの構造などを定義します。
一方、運用設計はシステムが完成したあとの維持や管理の方法、その体制づくりを担います。それぞれ目的が異なるため、設計時に取り扱うテーマも変わってきます。運用設計では、稼働後に想定される定例作業や障害対応、運用体制を見据えて設計する必要があります。そのため、設計段階から運用予定者が参画し、開発設計者と運用設計者の両者が連携して設計することが望ましいでしょう。
運用設計の種類
運用設計には大きく分けて以下2つの種類があります。
システム運用設計
システム運用設計とは、システムを安定的に運用するために必要なインフラやプラットフォームの運用方針・手順を設計することを指します。
具体的には、システムの監視方法、障害発生時の対応手順、バックアップおよびリカバリの設計、パフォーマンス管理、セキュリティ対策などが含まれます。システムの安定稼働を維持し、障害時にも迅速に復旧できるような設計が求められます。
運用業務設計
運用業務設計とは、システムを適切に管理し運用全体を統制するための業務設計を指します。
具体的には、ITILを活用した運用業務の洗い出し、業務フローやルールの策定、運用手順・マニュアルの作成などが含まれます。業務の効率化や正確性の向上を目的とし、現場の担当者が円滑に業務を遂行できるように設計することが重要です。
また、運用の品質向上やコスト削減を目的とした運用改善施策の検討も重要な要素です。
運用設計のメリット

ここでは、運用設計をおこなうことで得られる具体的なメリットを解説します。
運用開始の円滑化
運用を開始すると、実際の稼働状況に応じて監視の閾値や運用ルールを見直す必要が生じることがあります。その際、事前に運用設計をおこなっておけば、調整の手順や担当者の役割分担があらかじめ整理されているため、新任の担当者であっても迷わず対応しやすくなります。
また、設計情報が一元管理されていれば、担当者の交代時に必要となる引継ぎ作業の負担や時間を大幅に削減できます。
さらに、トラブルシューティングの方法を含めたノウハウを組織内で共有することで、特定の担当者に依存する属人化を防ぐことが可能になります。
運用範囲の明確化
運用には、システム管理者、ユーザーサポート、ネットワーク管理者などさまざまな関係者が関わります。設計段階でそれぞれの役割を整理しておくことで、責任の所在が曖昧になることを防ぎ、後々のトラブルを回避できるでしょう。
例えば、ソフトウェア更新やログ監視といった業務について、誰がどのような権限で実施するのかを明確にすることで、業務の抜け漏れや重複を防ぎ、効率的な運用が可能になります。
また、役割が重複している場合には作業の効率性を見直すきっかけにもなります。しっかり役割分担を整理することで、リソースを最大限に活用できる体制を築けるでしょう。
障害・トラブルの最小化と適切な対応
運用設計の段階で障害対応フローを定義しておくことで、問題が発生した際に担当者が迅速に対応を開始できる体制が整います。
また、問題の切り分けや原因特定の指針が明確になるため、対応の質と速度の向上が期待できます。
さらに、事前に監視項目や監視手順を設計に組み込むことで、エラー発生時に的確な警告を検知しやすくなります。これにより、障害の早期発見が可能となり、システムへの影響を最小化するだけでなく、ユーザーへの影響も最小限に抑えられるでしょう。
運用設計で検討すべきおもな項目

ここでは、運用設計の際に検討すべき項目について解説します。
基本方針
基本方針では、システムの運用における基本的な方針や目的を明確に定めます。
運用設計の指針となる重要な項目であるため、最初に策定し、設計プロセスの基盤を固めることが重要です。
また、基本方針は運用の見直しや変更時の判断基準にもなるため、ドキュメントとして整理し、組織全体で共有しておくことが不可欠です。
対象システムの詳細
運用設計の対象となるシステムの概要や仕様を整理します。
どのシステムが運用対象となるのか、また、その機能や利用者を明確にすることは、適切な運用設計を進めるうえで欠かせません。
例えば、システムが外部サービスと連携するのか、それとも内部で完結するのかによって、運用の手間や障害時の影響は大きく異なります。
こうしたシステムの特性を把握したうえで、バックアップの頻度や監視のタイミングを最適化することが、効果的な運用設計の鍵となります。
構成情報
システムのインフラやネットワーク構成、ソフトウェア構成などの詳細を整理します。
サーバ、ネットワーク、ソフトウェアバージョンなどの構成情報を一覧化することで、障害発生時の切り分けや原因追究が迅速におこなえるようになります。
また、クラウド環境かオンプレミス環境かによって必要な管理情報は異なるため、構成情報は常に最新の状態に更新しておくことが重要です。
さらに、機器の廃番やサポート期限の終了に備え、ライフサイクル管理の観点からも構成情報を整理しておくことが求められます。
運用体制
運用に関わる組織・担当者の役割や責任範囲を明確に定めます。
運用体制を構築するうえで、担当部署や人員配置を決定し、教育計画や連携方法を整理することが重要です。
例えば、24時間体制での監視が必要か、週末や夜間の管理・対応フローをどのように構築するかを具体的に定めます。複数のチームや外部の専門業者が関わる場合は、それぞれの責任範囲、管理ツール、そしてコミュニケーション手段を明確にしておく必要があります。これにより、異なる組織間でのスムーズな情報共有や迅速なトラブルシュートが可能になるでしょう。
さらに、運用担当者のスキルレベルに応じて研修や資格取得をサポートするなど、体制面の強化施策も考慮すると良いでしょう。エンジニアの育成は長期的な運用品質を左右する要素となります。
監視設計・障害対応の手順
監視設計、障害発生時の対応フローを策定します。
監視設計では、どの項目をどのタイミングで監視するのか、どのような閾値でアラートを発報するのかを決定します。これにより、障害の予兆を早期に検知し、システムダウンを未然に防ぐことが可能になるでしょう。
監視の粒度やアラートの条件を適切に設定することで、不要なアラートを抑制しつつ、異常の早期検知を両立させることが重要です。
障害対応手順では、担当者がとるべき初動の対応に加え、上位層へのエスカレーションフローを明確にしておく必要があります。迅速な対応を実現するために、連絡手段や連絡先の一覧を最新の状態に保ち、即座に行動を起こせる体制を整備します。
また、障害が解決したあとは、原因の分析と再発防止策として、システム設計や運用設計の見直しをおこない、改善点をフィードバックする仕組みを構築します。これにより、継続的な品質向上と運用の最適化を実現できるでしょう。
監視設計・障害対応手順は、システムの安定稼働を支える重要な要素であり、システムダウンによる影響を最小限に抑えるうえで非常に重要度の高い項目であるため、慎重に検討・精査することが求められます。
定常作業
定常作業とは、システムを円滑に運用するために定期的に実施すべき業務(定期的なバックアップ取得、アクセス権限の見直しなど)を指します。
これらの定例業務を計画的かつ確実に実施することで、トラブルの未然防止や迅速な対応につながるため、適切な管理が重要です。運用設計の段階で、各定常作業の実施頻度、チェック項目、担当者を明確にすることで、作業の漏れやミスを防ぎやすくなります。
また、作業完了報告のフローを事前に設定しておくことで、状態の把握がスムーズになるでしょう。
例えば、ソフトウェアやシステムに存在するバグや脆弱性を修正する修正プログラム(パッチ)適用時は、本番環境への影響を最小限に抑えるよう慎重に計画する必要があります。状況に応じて冗長構成を活用しながら段階的に適用するなど、システムの停止時間を短縮する工夫も求められます。
このように、定常作業を適切にスケジューリングし、確実に実施することで、より円滑な運用が実現できるでしょう。
▼エヌアイデイには50年以上大手航空会社様の大規模システムを運用してきた知見と体制があります。
運用設計のポイント

ここでは、適切な運用設計をおこなうために押さえておくべきポイントを解説します。
可用性を優先する
可用性とは、システムが停止することなく継続的に稼働し続けることを指します。
システムの停止による損害は大きいため、障害発生時の初動対応や復旧手順をあらかじめ整備し、許容される停止時間以内に復旧できることが求められます。
しかし、高い可用性を実現しようとすると、冗長構成の導入や監視体制の強化などにより、機器の導入費用や運用費用、設計工数が増大する可能性があります。そのため、サービスの目的や利用者の規模に見合った適切な可用性のレベルを設定することがポイントになります。
不特定多数の利用者がアクセスするシステムや常時稼働が求められるシステムは、システム停止による影響が大きいため、24時間365日の監視や即時対応ができる体制を整え、ビジネスの継続性を確保することが求められます。
一方、社内向けシステムのように、利用者が限定され、社会的影響が比較的小さい場合は、予算やリソースに応じた可用性の方針を策定し、コストと運用負荷のバランスを取ることが必要です。
機密性を重視する
機密性とは、システム運用において取り扱う情報が外部に漏れないように管理することを指します。
情報漏洩は企業の信用失墜や損害賠償といった重大なリスクを引き起こすため、運用設計において機密性を確保することは非常に重要です。
具体的な対策としては、アカウントやアクセス権の適切な付与・管理、セキュリティ製品の適切な導入・運用があげられます。
さらに、セキュリティログの収集と監視を徹底し、異常を早期に検知できる仕組みを構築することで、機密性が十分に保たれるような設計をおこなうことができるでしょう。
完全性を担保する
完全性の担保とは、システムが保有する情報が正確かつ安全で最新の状態である、ということを指します。
最新状態に更新する際の手順やマニュアルを適切に設計すること、アカウントやアクセス管理が適切かどうか確認すること、などがあげられます。正確さや安全さを意識することは多いのですが、最新の状態であるというポイントを忘れてしまいがちです。運用設計をおこなう際には、アップデートや情報の更新を忘れないよう、ルールにあらかじめ組み込んでおきましょう。
運用設計の外部委託を検討する
運用設計は検討項目が多く、専門的な知識も求められるため、社内のリソースだけでは対応が難しい場合があります。
そのような場合、専門業者へ外部委託することも有効な選択肢の一つです。
外部の専門業者からシステム運用に関するコンサルティングや、運用設計・構築のサポートを受けることで、社内の負担を軽減しつつ、運用の安定性を向上させることができるでしょう。
さらに、第三者の視点を取り入れることで、自社では見落としがちなリスクや改善点を明らかにでき、より実効性の高い設計につながっていくでしょう。ただし、設計をすべて任せきりにするのではなく、プロセスの中で自社の担当者も関与し、知識やノウハウを蓄積していくことで、将来的に自社の運用体制を強化していくことにつながるでしょう。
運用設計からシステム運用監視まで、トータルサポートならエヌアイデイにご相談ください

株式会社エヌアイデイは、50年以上にわたるシステム運用の実績と高度な技術力を活かし、システムの安定稼働を支える運用設計をご提供しています。
お客様の業務特性やシステム環境に応じて、最適な運用プロセスを構築し、効率的かつ安全な運用の実現をサポートします。
運用設計から24時間365日のリモート監視まで幅広く対応し、強固かつ柔軟な運用体制の構築もサポートします。システムの安定稼働とお客様のビジネスの成長を、運用の側面からしっかりと支えてまいります。
最適なご提案をさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ

運用設計はシステムを円滑に稼働させるうえで欠かせないプロセスです。本記事で紹介したポイントを踏まえ、最適な運用設計を実践してください。
運用設計を適切におこなうことで、システム障害や業務の混乱を最小限に抑えることができるでしょう。関係者全員が共通の指針を持ち、必要なドキュメントや手順書を整備することで、属人化の防止にもつながります。
さらに、開発と運用を切り離さず、設計段階から運用を意識することで、リリース後のトラブル削減や改善サイクルの効率化が期待できます。加えて、継続的な改善を重ねながら運用体制をアップデートし、サービス品質を高めていくことが重要です。
今後、運用設計はますます複雑化するIT環境において、企業が競争力を維持していくための要となるでしょう。
ぜひ本記事を参考に自社に適した運用設計の実践を目指してみてください。
▼大手航空会社様のミッションクリティカルなシステム運用監視の経験から、セキュアで高品質な運用監視を24時間365日ご提供します。
▼運用監視サービス「MesoblueMSP」の事例詳細はこちら
▼あわせて読む「MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは?サービスを導入するメリットや選び方を徹底解説」