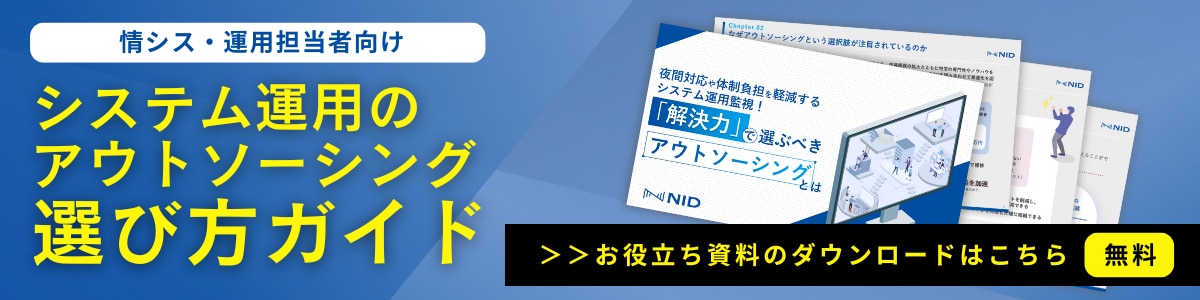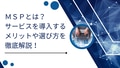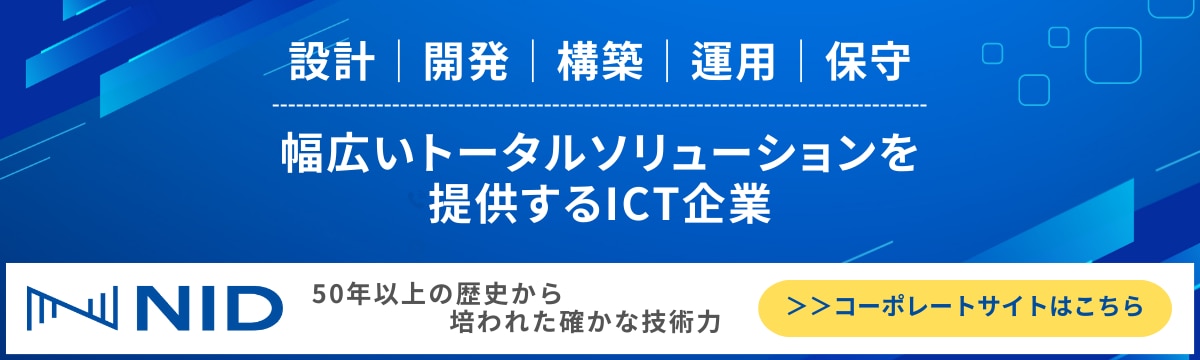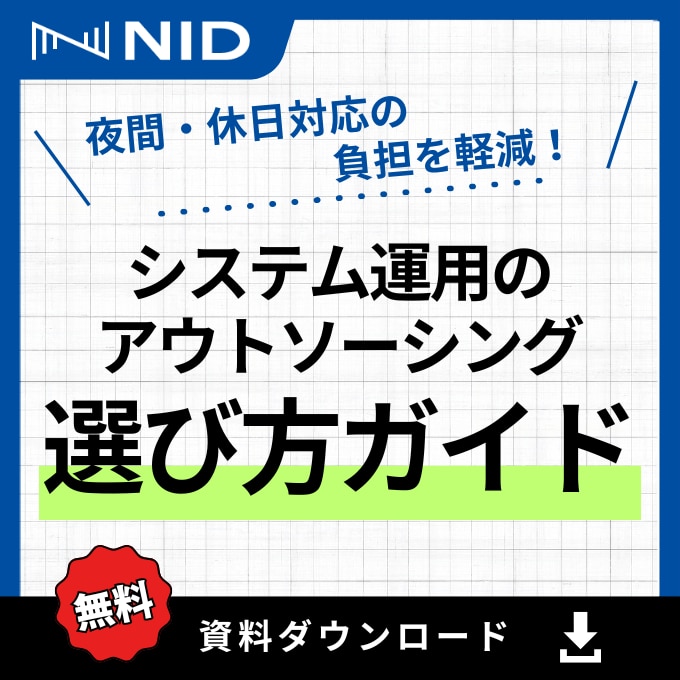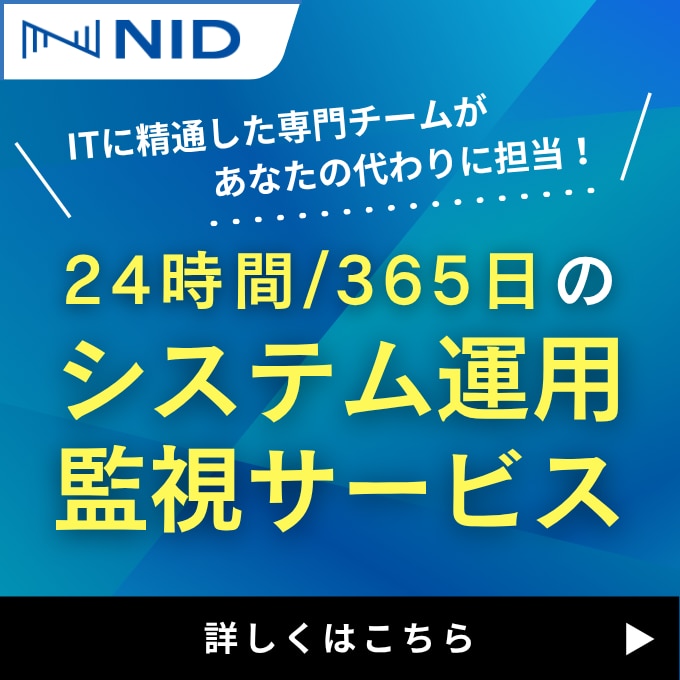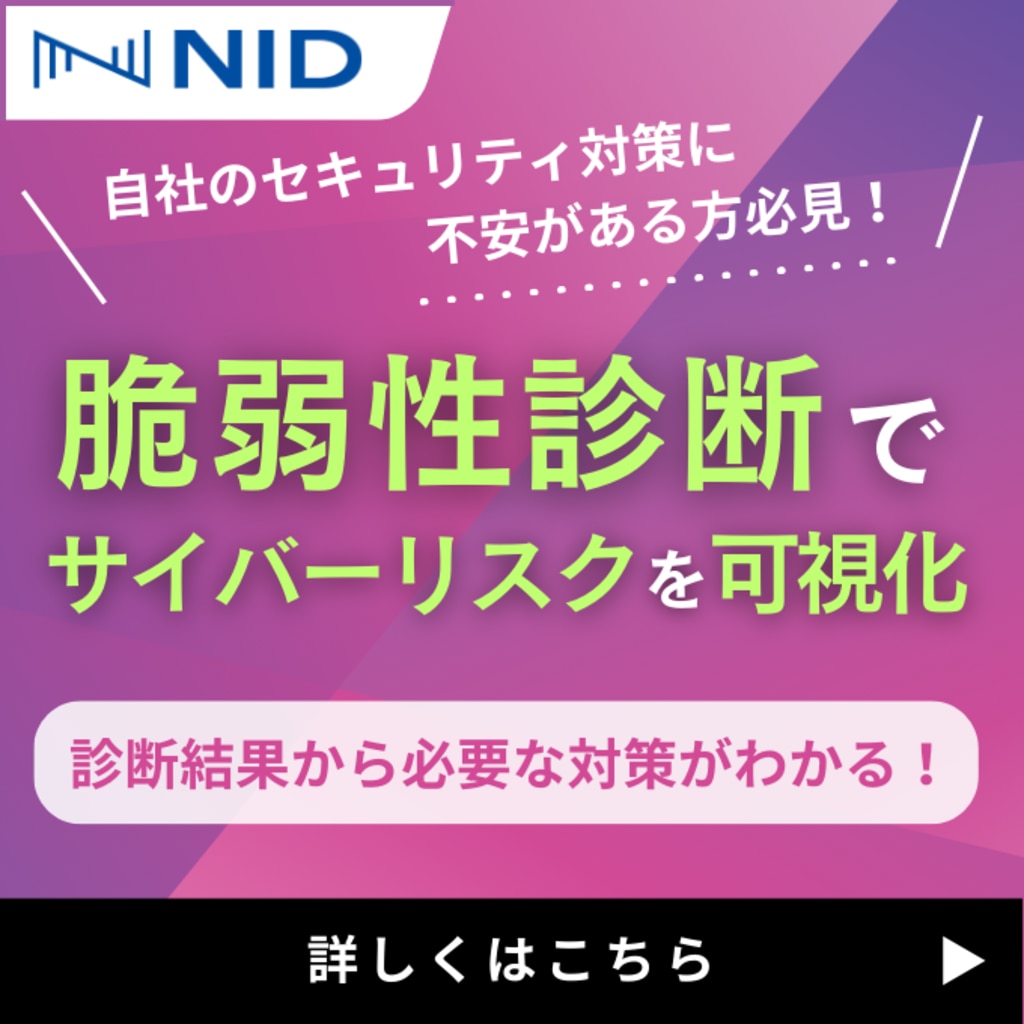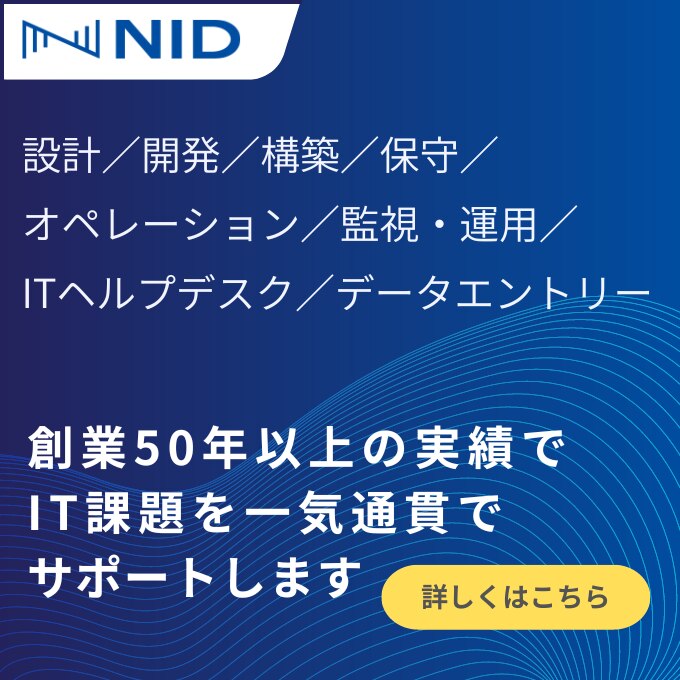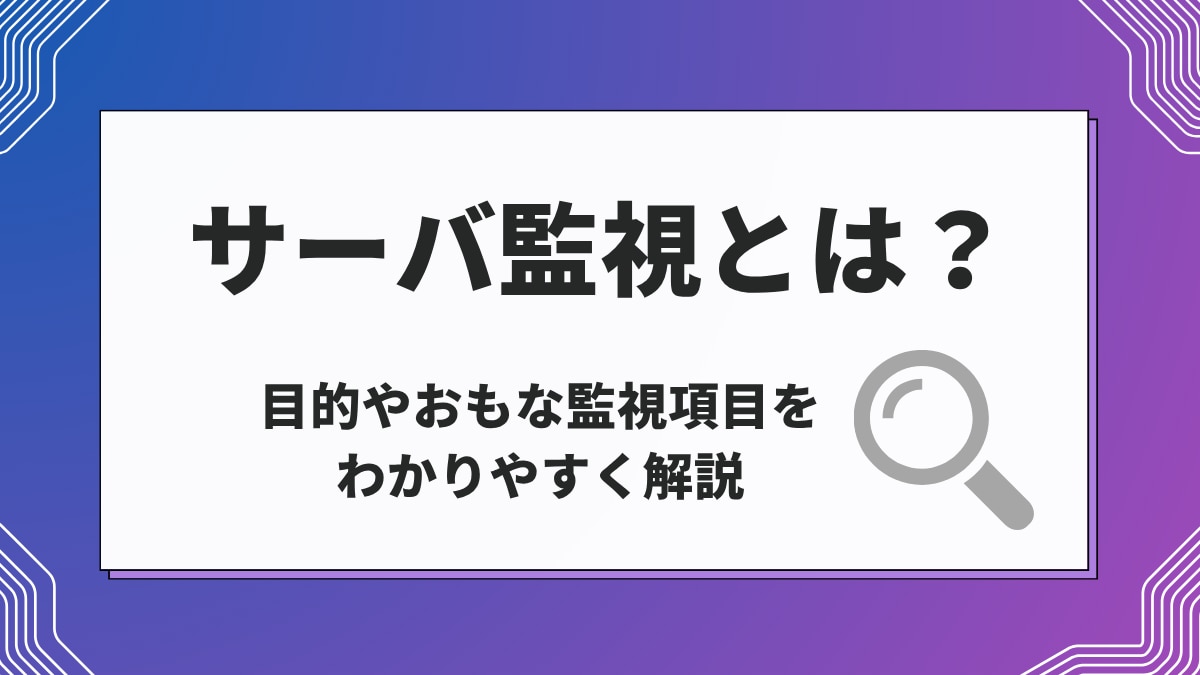
サーバ監視とは?目的やおもな監視項目をわかりやすく解説
サーバ監視はシステムの安定稼働を維持するうえで欠かせない作業です。適切な監視体制を構築することで運用中に起こりうる障害や不具合を効率よく検知し、有事の際もビジネスへの被害を最小限にとどめることができます。近年ではクラウドや仮想化技術の普及により、監視の対象となるサーバやサービスが増え、手法も多様化してきました。
ここでは、サーバ監視の基本的な考え方や監視項目、監視方法などをわかりやすく解説していきます。
INDEX[非表示]
- 1.サーバ監視とは?
- 2.サーバ監視の目的
- 2.1.障害の予防
- 2.2.障害原因の特定
- 2.3.パフォーマンスの最適化
- 3.サーバ監視の種類
- 4.サーバ監視で見るべきおもな項目
- 5.オンプレミスとクラウドでの監視の違い
- 6.サーバ監視をおこなう際に重要なポイント
- 7.サーバ監視の方法
- 7.1.監視ツールを導入する
- 7.2.アウトソーシングを活用する
- 8.サーバ監視をアウトソーシングする場合のポイント
- 8.1.監視範囲の明確化
- 8.2.通知・報告の方法・頻度
- 8.3.障害対応範囲
- 8.4.監視体制・監視時間帯
- 9.アウトソーシングの成功事例
- 10.24時間/365日のリモート監視・運用サービス「MesoblueMSP」
- 11.まとめ
サーバ監視とは?

サーバ監視とは、サーバの稼働状況を把握し、正常に動作しているかをチェックする作業です。万が一異常を発見した際は、サーバ管理者に知らせる仕組みが整っていることが望ましいです。
サーバ監視が適切におこなわれていない場合、異常時の発見が遅れ、重大な障害やデータ損失、サービスの停止に発展する恐れがあります。対象のシステムによってはサービス停止が社会インフラに影響を与え、多くの人々の生活に関わる事態を招く可能性もあるため、適切な監視が必要不可欠です。
サーバ監視の目的
サーバ監視の最大の目的はサービスの安定稼働を実現し、ビジネスを止めることなく影響を最小化することにあります。そのためには以下の3点が重要になります。
障害の予防
サーバ監視によって収集したリソース使用率やログを分析することで、障害の前兆をつかむことができます。例えば、メモリやストレージの使用量が一定の閾値を超え始めたなどの兆候を把握し、早期に対策を取れば重大な障害を未然に防げます。現場の運用担当者としても、随時データを蓄積しておくことで分析ができ、予防施策の立案が容易になります。
障害原因の特定
障害が発生した際は、ログの解析やプロセスの状態把握などが原因究明の手がかりとなります。適切に監視をおこなっていれば、障害が生じたタイミングや異常値を示す記録がすぐに参照できます。問題を迅速に切り分けて原因を特定することで、復旧時間を大幅に短縮し、システム停止による影響を最低限に抑えることが可能になります。
パフォーマンスの最適化
監視で得られるデータを活用し、サーバのパフォーマンス改善に役立てることもできます。特にクラウドの場合は、CPUやメモリの負荷状況、レスポンスタイムなどを詳細に把握することで、設定の見直しや上位スペックへの移行、リソースのスケーリングなどの施策を検討できます。
パフォーマンスの最適化を図ることで、ユーザー体感速度の改善やサービスクオリティの向上につながり、ビジネスチャンスの損失を防ぎます。
サーバ監視の種類

サーバ監視には、大きく分けて正常監視と異常監視の2種類があります。正常監視は通常通り動作している状態を管理し、異常の兆候をいち早くつかむ役割を担います。一方の異常監視は、障害が発生したときに素早く検知し、通知をおこなうことが主目的となります。
どちらもサーバの安定稼働を確保するうえで欠かせない要素です。
正常監視
正常監視は、サーバやネットワーク機器が定常的に稼働しているかをチェックする仕組みです。例えば、CPU負荷やメモリ使用量、ディスク容量を定期的に計測し、トレンドに異常がないかを確認します。これにより、急激にリソースが逼迫した場合には障害発生の前触れとして察知し、事前対応が可能になります。
異常監視
異常監視では、サーバに問題が起こった際、即座に障害を検知して通知をおこなうことに主眼を置きます。死活チェックなどでダウン状態を見つけたり、サーバを構成しているハードウェアやOS、ミドルウェア、アプリケーションといった各要素が応答しなくなった際にアラートを送信するなど、多様な仕組みを活用します。迅速な対応が求められるため、通知の設定は管理者にメールを送る方法や、監視画面上でアラートを表示する方法、さらにはコールセンターとの連携なども検討されます。
サーバ監視で見るべきおもな項目

サーバ監視では、死活監視やリソース監視、ログ監視など、サーバの用途に応じて多岐にわたる項目をチェックする必要があります。監視の範囲が広いほど、問題が発生した際の切り分けや原因特定が容易になる一方で、運用コストも増えるため、システムの規模や重要度に応じて最適な監視項目を選定することが大切です。
代表的な監視項目を以下にご紹介します。
死活監視
死活監視は、サーバが稼働しているか(停止していないか)をチェックする最も基本的な監視項目です。代表的なPing監視をはじめ、HTTP監視やプロトコル監視などがあります。実際の現場ではどれか一つではなく、これらの監視を組み合わせて使うことが一般的です。例えば、Ping監視でサーバの応答を確認し、HTTP監視でWebサイトの動作を確認し、さらにプロセス監視でアプリケーションの動作を見守る、といった形です。
Ping監視
Ping監視は、死活監視の中でも最も基本的な方法です。
Pingコマンドを用いてサーバに向けて「ICMPパケット」という信号を定期的に送ります。サーバが稼働していれば応答パケットを返してくれるため、応答可否を定期的に確認することで稼働状態を監視します。
HTTP監視
HTTP監視は、Webサーバの監視で使われます。Webサーバに対してHTTPリクエストを定期的に送信し、応答コードや応答時間を確認し正しく動作するかを監視します。HTTP監視を適切におこなうことで、ユーザーがWebサービスにアクセスできない事態が生じた場合もいち早く検知できます。
プロセス監視
プロセス監視は、サーバ上で動作している特定のプロセス(データベースやアプリケーションの動作)が正常に起動・稼働しているかを監視します。Webサーバプロセスやデータベースプロセスが停止しているとサービス全体が機能しなくなる恐れがあります。プロセス監視を定期的におこなっておけば、万が一プロセスが止まってもすぐに発見でき、サービスダウンを最小限にとどめられます。
リソース監視(パフォーマンス監視)
リソース監視は、CPU使用率やメモリ、ディスク使用量、ストレージ残容量など、サーバが利用するリソースの消費状況を監視します。定常的に監視・記録することで、急激な負荷の増加や将来的なリソース不足を予測し、早期対策につなげることが可能です。
ログ監視
ログ監視は、サーバが生成する各種ログ(システムログやアプリケーションログ、セキュリティログなど)を定期的に確認し、出力されるエラー・警告メッセージを解析することでトラブルや潜在的な問題を早期に発見する監視方法です。問題が生じる前の微妙な異常を示すログが書き込まれるケースもあり、定期的なログのチェックはリスク管理に大きく貢献します。
ポート監視
ポート監視は、特定サービスのポートへの接続が正常におこなえるかを確認し、サービスの動作状態を監視します。HTTPやFTP、DNSなど、業務上重要な通信プロトコルが正しく応答しているかを定期的にテストすることが肝要です。死活監視よりも一歩踏み込んだレベルでサービスの可用性を把握できるため、障害対応の迅速化につながります。
オンプレミスとクラウドでの監視の違い
物理サーバを自社管理するオンプレミスとクラウドサービスを活用する場合では、監視の手法や留意点に違いがあります。
オンプレミス環境ではハードウェアからネットワーク機器まですべて自社で保守するため、障害が発生した際には物理的な原因調査や、電源、設備系統の確認も監視項目に含まれます。
一方、クラウド環境はサービス事業者の提供するインフラ上で稼働するため、監視の範囲はオンプレミス環境よりも狭まります。また、仮想マシンの切り替えや冗長化も比較的容易に実施できるため、運用負荷の軽減が期待できます。ただし、監視そのものが不要になるわけではありません。自社で管理する部分を明確に把握し、クラウド特有の管理権限設定も適切におこなうなどの対応が必要です。
オンプレミスとクラウドどちらを採用するかで管理範囲が変わるため、監視対象を明確にし、必要なツールや監視項目をあらかじめ検討しておくことが重要です。
サーバ監視をおこなう際に重要なポイント

まずは、必要な監視項目をシステムの特性や利用規模に合わせて精査することが重要です。過度に細かい監視をおこなうとアラートが頻発し、運用担当者の負担を増やしてしまう可能性もあります。適切な閾値設定やアラート条件の見直しによって誤報を減らし、異常の際に素早く対応できる体制を構築することが求められます。
サーバ監視の仕組みの構築には専門知識やノウハウが求められるため、有識者のアサインが重要です。
サーバ監視の方法
サーバ監視には、自社で監視ツールを導入する方法と、専門のアウトソーシングサービスを利用する方法があります。どちらの方法にも一長一短があり、システムの規模や予算、運用体制などに合わせて選定することが大切です。
監視ツールを導入する
自社で監視ツールを導入する場合は、責任範囲が明確で、自社に合わせた設定で運用できる点がメリットです。オープンソースのツールを選べばライセンスコストを抑えられるほか、詳細な設定によって自社の運用に合わせた監視体制を構築できます。反面、ツールの導入やメンテナンスに一定の知識と人員が必要になるため、担当者の育成や作業工数の確保が課題となります。
アウトソーシングを活用する
監視業務を専門ベンダーに委託することで、24時間365日の監視体制を実現できます。自社に十分な人員やノウハウがない場合、アウトソーシングは魅力的な選択肢です。ただし、システムの詳細を外部に任せることになるため、情報共有の精度やセキュリティ面に配慮が必要となります。契約内容や監視範囲を明確にし、密な連携を図ることでメリットを最大化できます。
サーバ監視をアウトソーシングする場合のポイント
サーバ監視のアウトソーシングを検討する際は、自社の要望に適切に応えてくれるベンダーを見つける必要があります。あらかじめ自社で整理しておくべきポイントや選定時に確認すべき点をいくつかご紹介します。
監視範囲の明確化
前述したように、監視対象によって監視項目は多岐にわたります。アウトソーシングする際はなにを監視してもらうのかを最初に細かく整理しましょう。監視対象を委託側でリスト化しておくとスムーズに調整が進みます。
通知・報告の方法・頻度
監視の結果、異常が発生した際に誰に・どう通知するのかをあらかじめ決めておく必要があります。
通知手段(メール/電話/SMS/チャットツール(Slack, Teamsなど))
通知先(担当者不在時を考慮し、複数人設定することを推奨)
エスカレーションルール
障害対応範囲
サービスによっては「監視まで」「通知まで」としているところも多くあります。「障害対応(復旧対応)」まで含まれるかはサービスによって異なるため、一次対応や二次対応まで依頼したい場合は事前に確認が必要です。
パターン | 内容 |
|---|---|
監視通知のみ | 異常時に知らせてくれる |
一次対応あり | 簡単な再起動や設定変更まで対応 |
フルマネージド | 原因調査・復旧・報告まで対応 |
監視体制・監視時間帯
24時間365日監視してくれるのか、日中だけなのか、監視体制と時間帯も契約前に確認しましょう。「夜間も監視」でも、通知だけで対応は翌営業日、といったパターンもあるため注意が必要です。
アウトソーシングのサービス全般についてもっと詳しく知りたい方は、MSP(マネージドサービスプロバイダ)について解説しているこちらの記事もご参照ください。
▼あわせて読む「MSP(マネージドサービスプロバイダ)とは?サービスを導入するメリットや選び方を徹底解説」
アウトソーシングの成功事例

エヌアイデイが監視および運用保守のアウトソーシングを請け負い、お客様の課題を解決した事例をご紹介します。
お客様はエヌアイデイへのアウトソーシング以前、障害発生時の作業負担や社内のリソース不足などを課題としてお持ちでしたが、エヌアイデイへアウトソーシングいただいたことでシステムの安定稼働に加え、業務負荷の大幅減を実現いたしました。
- アウトソーシング前の課題
障害対応を含む運用を自社でおこなうため多くのリソースを必要とする
障害発生時にはオンサイトでの復旧作業が避けられない
運用に関するナレッジが担当者の中だけに蓄積され属人化している
- アウトソーシング後の変化
リソースの確保から解放され、コア業務に専念できる環境が実現
障害発生時における復旧対応業務の負荷が大幅に軽減
属人化が解消され、ナレッジはいつでも伝承できるものへと進化
▼全日空商事株式会社の導入事例インタビューの全文はこちら
24時間/365日のリモート監視・運用サービス「MesoblueMSP」
「MesoblueMSP」はエヌアイデイが提供する24時間/365日のリモート監視・運用サービスです。大手航空会社の大規模システムを50年以上運用してきた実績で、お客様の大切なサービスを24時間/365日で監視・運用いたします。
障害検知から障害一次対応、システム運用設計から改善まで、サーバの運用・監視にまつわるお困りごとは「MesoblueMSP」 にご相談ください。
まとめ

ここではサーバ監視の重要性や具体的な監視項目、監視手法などを一通りご紹介してきました。
適切なサーバ監視をおこない、日々の稼働状況を把握することで障害発生時にも迅速な検知と対処が可能になります。最適な監視体制を構築し、継続的な運用・改善をおこないながらビジネス活動の根幹を支えるサーバを常に安定させるのは、どのサービスにおいても重要です。
エヌアイデイは、50年以上にわたる実績と経験に基づいた高品質な運用監視サービスを、IT系企業や製造系企業など多くのお客様にご提供しています。自社の監視体制に少しでも不安がある方はお気軽にご相談ください。